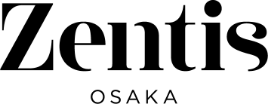大阪の西天満を東西に横切る老松 (おいまつ) 通りは骨董商や画廊がずらりと連なる関西随一のアートストリート。名物は毎年春と秋に開催される老松古美術祭。世代・性別・国籍を問わず古美術品やアンティークを求める人々でにぎわいます。祭の実行委員でもあるギャラリー帝塚山の堀田実さんとともに、老松通りが紡ぐ物語をひもときます。
老松通りは古美術店が集まる大阪屈指の芸術の街
都会の喧騒を忘れさせてくれる、大阪・西天満の一角に「老松通り」はあります。
約1kmにわたって続くこの通りには、およそ90軒もの古美術店や画廊がひしめきます。東洋古美術、茶道具、西洋アンティーク、古今の絵画、現代美術まで、取り扱う品物はさまざま。ここを歩けば、まるで芸術の歴史を旅しているような気分になります。


「老松」の名は、樹齢の長い松が植えられた老松神社がこの場所にあったことに由来し、区画整理で神社や地名がなくなった現在も老松町の愛称で呼ばれる場合があります。昭和になって東京の名だたる古美術店が移転してきたのをきっかけに、骨董商や画廊が集まるようになったとのこと。
そんな気品ある通りを歩いていると、目的地のギャラリー帝塚山に到着。
ここは、実は老松通りのアートシーンをけん引する存在です。

30年以上にわたって審美眼を鍛えた2代目当主
1973年に開業したギャラリー帝塚山。扉を開けた瞬間、まるで美術館のような空気に包まれ、思わず見入ってしまいます。中国、李朝などの古美術品、西洋の古陶磁器からインドの仏教美術まで、ワールドワイドな品揃えなのです。

18歳の若さで古美術の世界に入り、30年以上にわたって鑑定や売買をし続け、2018年に2代目を継承した堀田実さんは、こう語ります。
「目利きは買うことで鍛えました。真贋 (※) を誤ると経営が傾きますから真剣勝負。お客さまのなかには私よりも目が肥えた人たちがたくさんいます。そんな達人を相手にするのだから、度胸も据わりますよ」 (堀田さん)
※真贋 (しんがん):本物 (真) と偽物 (贋)

世界をめぐって極上の美術品を入手する堀田さん。それだけに海外からのお客さまも多いのだそうです。
「近年はシンガポールやマレーシア、ベトナムからお見えになるお客さまが増えました。接客を通じて、不思議と世界経済がどのような流れにあるのかが見えてくるんです」 (堀田さん)
景気が上向くと、古美術を投資や趣味として楽しむ方が増えてくる──。
まさに “世界経済の縮図” のような場所なのです。
骨董への間口を広げた老松古美術祭の意義
堀田さんにはもう一つ、老松古美術祭の実行委員という顔があります。
老松古美術祭とは春と秋の年2回開催される骨董・古美術のイベントです。

阪神・淡路大震災の復興支援を目的に1995年から始まり、先ごろ55回目を迎えました。堀田さんは初回から運営に携わっています。
「はじめたころはパソコンがまだ普及していなかった時期で、ワープロでパンフレットをつくったり、他店の商品も撮影したり、コンビニでカラーコピーを取ったり、なかなか大変でしたね」 (堀田さん)
しんどい思いをしながらも祭の成功へ向けて尽力したのは、ある想いが胸にあったから。
「古美術といえば中高年の趣味というイメージが強く、若者から敬遠されがちだった。だから間口を広げたかったんです。おかげさまで20代~70代まで幅広い年齢層が集うイベントになりました」 (堀田さん)

そんな堀田さんが勧める、古美術の楽しみ方とは。
「たとえば江戸時代の焼きものなら、『昔の人はどんな食生活を送っていたのだろう』と思いを馳せてみる。想像力が豊かになるし、文化的な知識も増えてきて、よりいっそう楽しくなるんです」 (堀田さん)
古美術って難しいかもと躊躇しているのならば、老松通りを訪れてみませんか。
古いものを知ることで、新しい扉が開くかも。
記事の内容は掲載日 (2025年10月) 時点の情報です。

INFORMATION
ギャラリー帝塚山<老松古美術祭事務局>
大阪市北区西天満4-2-4 美術ビル
10:00 am - 5:00 pm
土・日・祝定休